前回の日本人の食事摂取基準(2020年版)におけるエネルギーに関する記述の要点に引き続いて、今回は同基準に基づく私のエネルギー摂取量と体重・BMIの管理等について書きます。
前回のまとめ(私なりに解釈した「エネルギー」に関する結論)において、「生命と健康長寿のため、良質なエネルギーを適正量(出来るだけ過不足ゼロに近く)かつ安定的に摂り続けたいと考えています。」と書きました。
しかしながら、日本人の食事摂取基準(2020年版)を繰り返し読んでも、自分にとってのエネルギーの適正量がどの程度なのかよく分かりませんでした。今でも完全に分かったとは言えず、試行錯誤を繰り返している状況です。
以下はこうした現状を踏まえての内容です。
エネルギー摂取量と体重・BMIの管理の経緯と現状
摂取エネルギー量と体重・BMIの推移
昨年の健康診断受診時頃(2023年11月)
この頃に私が食べていた食品に含まれているエネルギーを「食品成分データベース」で検索しNumbersで集計した摂取エネルギーは2,400〜2,500kcal/日でした。
一方、私の体格は体重57.5kg、BMI22.2kg/m2で、目標とする BMI の範囲(21.5~24.9)の平均値より若干低い程度であり、この体重と活動レベルⅢ(高い)を用いて、体重当たりの推定エネルギー必要量から必要量を計算すると、42.1kcal/日×57.5kg=2,420kcal/日となり、摂取エネルギーと概ね同等でした。
他に考慮要素が無ければ、この状態を維持していれば良かったのですが、未だ残っていた逆流性食道炎の軽い症状(胸焼け)を完全に解消するため、エネルギー摂取量を徐々に減らすとともに、16時頃〜17時頃であった夕食時間を更に早めてきました。
このブログを書き始めた頃(2024年8月上旬)
エネルギー摂取量を減らし、夕食時間を更に早めることによって体脂肪、体重、BMI、腹囲が減少するに伴い逆流性食道炎の症状が軽くなり、体重51kg(身長161cm)BMI19.7kg/m2程度まで減少すると、在宅時や歩行時、自転車を普通に漕ぐ程度の軽い運動時等は症状が完全に無くなりました。
この体重と活動レベルⅢ(高い)を用いて、体重当たりの推定エネルギー必要量から必要量を計算すると、42.1kcal/日×51kg=2,147kcal/日となり、その程度のエネルギーを摂取していました。
現在(2024年12月下旬)まで
その後も体重が減少し続けたため、朝食のオートミールを増やしたり、朝食後にバナナを食べるなどエネルギー摂取量を徐々に増やして2,300kal/日程度にしましたが、その後も体重減少が止まることなく50kgを下回り、BMIが自治体の健康診断における下限基準である18.5kg/m2に近づいて、流石にこれ以上下げるのは問題があると考え、エネルギー摂取量を段階的に大幅に増やしました。
エネルギー摂取量を増やすために蛋白質の摂取を増やすことは出来ないので、蛋白質を含まず、かつ、血糖値を上げない食品はないかと消去法的に色々と考えた末、MCTオイルを摂り始めました。
MCTオイルの摂取量は、最初、10g/日(朝食時と夕食時に各5g)から始めて徐々に量を増やし、現在は40g/日(朝食時と夕食時に各20g)を摂取しています。これによって、エネルギー摂取量を2,700kcal/日近くまで引き上げ、現在、体重50〜51kg、BMI19.3〜19.7kg/m2を維持しています。
またこの体重から、体重当たりの推定エネルギー必要量で必要量を計算すると、42.1kcal/日×50.5kg=2,126kcal/日となます。
エネルギー摂取量を増やした(約2,400kcal↘️約2,150kcal↗️↗️約2,700kcal)にも関わらず体重が減少した(約58kg↘️約51kg)要因
夕食時間を早めてきた効果
1 消化器官等の内臓を休ませるとともに内臓脂肪を減少させて、持病である逆流性食道炎を改善するため少しづつ夕食時間を早めてきました。そして、昨年の今頃における夕食時間は16時頃〜17時頃でしたが、それから更に約2時間早めて現在の夕食時間は14時頃〜15時頃とし、朝食(6時頃〜6時半頃)まで約15時間の間隔(空腹時間)があります。
この空腹時間中における糖新生やケトン体産生によって体脂肪が減少したことは間違いないと考えています。
2 夕食時間を早めてきた理由は、1の通り、空腹時間中に体脂肪を減らして逆流性食道炎を改善するためでしたが、結果的にインターミッテント・ファスティング (次項参照)の効果であると言われているインスリン感受性の向上或いはインスリン抵抗性の低下によって、食後における糖の細胞への取り込みと燃焼量が増加していることも考えられます。
3 1年間で体重は7kg以上減少しましたが、脹脛(ふくらはぎ)の周囲長は昨年より若干長くなっており、また、見た目では上腕筋も若干増えているので、減少した体重以上に体脂肪が減少し、その分筋肉量が若干ながら増加したことによりエネルギー消費量が増加していると考えています。
なお、昨年と今年の運動量はほとんど変わらず、蛋白質の摂取量は減らしているので筋肉量が増えている理由は不明ですが、インターミッテント・ファスティングの効果としてオートファジーによって修復、再生された筋細胞が増加・増大等しているのかもしれません。また、同効果として修復、再生された筋細胞以外の細胞のエネルギー代謝量も増加しているのかもしれません。
インターミッテント・ファスティング(Intermittent fasting/断続的断食)
ネット検索するとファスティング、16時間断食等々として、脂質や炭水化物の代謝促進、脂質異常の改善、オートファジー等の効果があるといった情報があり、ダイエット目的で実施されている方も多いようです。
一方、最近、心血管疾患による死亡リスクが上昇したといった報道があったり、栄養不足、フレイル、血糖値の急激な変動等の危険があるといった情報もあります。
わたしの場合、夕食時間を早めてきた理由は、前述したとおり逆流性食道炎を改善するためだけであり、上記のような効果を期待してではありませんでしたが、結果的に前述したような(私にとっては)副次的な効果も得られているようです。
インターミッテント・ファスティング(断続的断食)のやり方についても、1日の中で食事可能時間と断食時間を区分する16時間断食や、1週間等複数日の中で食事可能日と断食日を繰り返す1日断食(24時間断食)等様々なやり方があるようです。
私の場合、丸一日食事をしないというのは絶対にしたくないし、仮に始めたとしても食欲に抗し難く続かないと思います。
また、16時間断食の場合、多くは、夕食は普通の時間に食べて、朝食を抜いたり、遅くする方法が紹介されていますが、私は、朝食を抜くというのには抵抗感があり、無理だと思いますので、夕食時間を早くする以外の選択肢が無く定職に就いていた時はしたくても出来なかったと思います。
エネルギーの主要な摂取源
多様な食品をバランス良く
生命と健康長寿に必要な栄養素や機能性成分を出来るだけ多く含み、かつ、命と健康に悪い成分が出来るだけ少ない多様な食品をバランス良く食べるよう心がけています。
その結果として、健康に悪いとされている不飽和脂肪酸を多く含む動物性の食品が少なく、様々な栄養素や機能性成分を豊富に含む植物性の食品が多くなっています。
また、結果的に多様な食品からエネルギーを摂取することが出来ています。(MCTオイルに偏重しているのは前述した理由によります。)
主なエネルギーの摂取源となっている食品(上位10食品)
実際の1日における食品の種類は日によって変動しますがこれらの食品の多くはほぼ毎日食べているものであり、「干し芋/むき甘栗」はその日によって何かを食べています。
また、「鶏胸肉/鮭/鯖缶/鰯缶等」は週に2〜3回この中の何かを食べています。
それぞれの摂取量も日によって変動しますので1日当たりの概算的な平均摂取量です。
| 食品 | MCTオイル | ナッツ類 | オカラクッキー | オートミール | バナナ | ココナッツミルク | 鶏胸肉/鮭/鯖缶/鰯缶等 | 黒胡麻 | 干し芋/むき甘栗 | 豆乳 |
| 食品摂取量(g) | 40 | 30 | 35 | 40 | 170 | 80 | 20 | 200 | ||
| エネルギー摂取量(kcal) | 360 | 170 | 160 | 160 | 160 | 150 | 130 | 130 | 110 | 110 |
エネルギー産生栄養素バランスの現状
MCTオイル摂取前後におけるエネルギー産生栄養素バランス
前述したとおり、最近、体重・BMIを維持するため、MCTオイルを摂り始めましたが、その前後におけるエネルギー産生栄養素バランス(% エネルギー)は次のとおりです。
| 栄養素 | 目標量 | MCTオイル摂取前の エネルギー摂取比率 | MCTオイル摂取後の エネルギー摂取比率 |
| たんぱく質 | 15~20 | 15.7 | 13.7 |
| 脂 質 | 20~30 | 33.3 | 41.7 |
| 飽和脂肪酸 | 7 以下 | ||
| 炭水化物 | 50~65 | 51.1 | 44.6 |
私は、日常の食事においては揚げ物、炒め物、脂身のある肉や精精油を一切摂っていませんでした。
そして、MCTオイルを摂り始める前でも、脂質が占めるエネルギー比率が目標量の上限を若干(3.3%)超える33.3%でしたが、前述のとおりMCTオイル摂り始めたことによりその超過量は更に増えて目標量の上限を11.7%超える41.7%となっています。
脂質の主要な摂取源
脂質については後日書きますが、前項のとおり、エネルギー産生栄養素バランスが脂質に偏っているため、参考として、脂質の主な摂取源となっている食品(上位10食品)を書きます。(脂質量は1日当たりの平均摂取量)
脂質は、蛋白質や炭水化物の2倍近いエネルギーがありますので、本表の食品の多くは、「主なエネルギーの摂取源となっている食品(上位10食品)」と重なっています。
また、脂質についても多様な食品から摂取しています。
これらは、何も、体重・BMIを維持するためのエネルギーや健康に必要不可欠な栄養素の摂取源となっている食品であり、脂質摂取量を目標量内にするためにこれらの食品の摂取量を減らした場合、エネルギーや栄養が不足することになります。
今後のエネルギー摂取量の管理
体重(体脂肪)が減少しても、筋肉量は昨年より若干増加しているので現状においてはフレイルの心配は全くありませんが、二度目の人生における八歳の健康診断結果 2 体格・血圧・脂質の血液中の脂質(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)で書きましたとおり、既に、中性脂肪やコレステロールが減少し(過ぎ?)たことにより皮脂やホルモンの分泌量が減少したように感じていますが、体重が低過ぎることにより何らかの別の問題が発生するかもしれません。
そのため、目標とする BMI の範囲(21.5~24.9)までBMI(体重)を戻したいと考えています。
しかしながら、単にBMI(体重)を戻すだけだと、逆流性食道炎を改善するための今までの努力が無駄になりかねません。
また、現在のエネルギー摂取量2,700kcalでも、体重当たりの推定エネルギー必要量から必要量を計算した2,126kcal(42.1kcal/日×50.5kg)を大幅に超過(約600kcal)しているのでこれ以上増やすことは好ましくないと考えています。
夕食時間を早めたことが体重減少の原因であるなら、これを遅くすれば体重も元に戻るはずですが、空腹時間を長くすることは体脂肪を減少させる以外の効果もあるようなので、出来れば現在程度の空腹時間は維持したいと考えています。
以上のことから、逆流性食道炎をぶり返さないで、空腹時間は現在(約15時間)程度を維持し、エネルギー摂取量を現在(2,700kcal)以下に減らしながら、BMI(現在19.7kg/m2)を目標とする BMI の範囲(21.5~24.9)まで戻す方法がないか色々と勉強しているところです。
今後のエネルギー産生栄養素バランスの管理
前述したとおり、現在のエネルギー産生栄養素バランスは脂質に偏っていますが、逆流性食道炎のぶり返し防止、体重・BMIの維持、栄養素の摂取の全てを満足するためには、脂質を多く含む食品の摂取量を減らすことは難しいです。
また、二度目の人生における八歳の健康診断結果 1 腎機能から同3 糖代謝・肝機能・尿酸・貧血までで書きましたとおり、健康診断の結果と体調で判断する限り、こうした食事を続けてきた私の健康状態は8年前に迎えた還暦で現世に再誕して以来、右肩上がりで良くなっているので、今後、何らかの不調等がない限りは現在のバランスで良いかなと考えているところです。
エネルギーを適正量摂取する重要性
昨今の健康ブームを反映して、ネット上には健康や食生活・食事についての情報が溢れていますが、特定の食品、例えば、炭水化物と脂質のどちらが良いか、肉と魚のどちらを食べるべきかとか、特定の栄養素、例えば、ビタミンDが重要、カルシウムを沢山摂ろうといった各論が多く、エネルギーに触れた情報がほとんど見当たりません。
私も、一度目の人生を含む私の人生において最悪の健康状態となり、本気で生活習慣の改善に取り組み始めた頃、その手始めとして大学以来学び続けてきた生物化学(生化学)や栄養化学等の知識を基に「日本人の食事摂取基準」の勉強を始めましたが、各栄養素の前にエネルギーについて詳しく書かれていることに疑問というか、戸惑いを覚えました。
そして、今まで書いてきました私が抱えているエネルギー摂取に関する問題を解決するために勉強したくとも、参考となる資料を探すだけでも相当な時間を費やしてきました。
そうした中、細々と勉強を進めながら、当時、最悪の健康状態の最大原因と思われた肥満を解消するために、食材等の計量は目分量等で、蛋白質、ビタミン、ミネラルが不足しないように多めに、糖質や脂質は過剰にならないよう少なめにと大雑把な計算で済ませながらも、摂取エネルギーだけは食事摂取基準の推定エネルギー必要量を目安として管理した結果、数年で体重・BMIを含む健康診断結果の全数値を正常参考値の範囲内に戻すことができました。
また、最近になって、当時の食事内容を思い出しながら計算してみると、エネルギーを適正量摂取することによって、結果的に、蛋白質は過剰摂取していましたが、ビタミンやミネラルを含むその他全ての栄養素の摂取量は基準を概ね満たしていたことが分かりました。
私は、現在は腎機能の悪化を防ぐ等の理由から、Numbersで主要なビタミンやミネラルを含む5大栄養素の摂取を詳細に管理していますが、最小限、穀物、野菜、果物、魚、肉といった多様な食品をバランス良く食べながら、栄養管理の基本であるエネルギーを適正量摂取するよう管理していれば必要とする栄養素を概ね過不足なく摂取できるものとも考えています。
次回から蛋白質と不可欠アミノ酸(必須アミノ酸)の摂取基準と摂取量等について書きます。
本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項
「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。
下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。



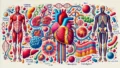
コメント