前回の認知機能低下及び認知症と栄養との関連、高齢者における食事摂取基準等に引き続き、今回は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」における高齢者の食事摂取基準に基づく私の摂取量について書きます。
高齢者の食事摂取基準に基づく私の摂取量
以下の内容は二度目の人生における健康的な食生活42〜88で書いた内容の要約ですが、その後の食事内容や量の変化により各栄養素の摂取量等も若干変化しています。
エネルギー摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のエネルギー摂取量は2,600〜2,700kcal/日で、身体活動レベルⅡ(2,400kcal/日)とⅢ(2,750)の中間よりⅢに近い摂取量となっています。
エネルギー摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等についてはエネルギー摂取量と体重・BMIの管理の経緯と現状をご参照ください。
たんぱく質の摂取量、エネルギー摂取比率と摂取源としている主な食品等
私の現在のたんぱく質摂取量は推奨量(60g/日)を30g/日〜40g/日上回る90g/日〜100g/日でありやや過剰摂取気味となっていますが、タンパク質のエネルギー摂取比率は15%で目標量(15〜20%)の下限程度です。
たんぱく質の摂取量の詳細、やや過剰摂取気味となっている理由と摂取源となっている主な食品等については生命と健康長寿に必要な蛋白質と必須アミノ酸の摂取基準と摂取量等2及びエネルギー産生栄養素バランスの現状をご参照ください。
脂 質
脂質のエネルギー摂取比率と摂取源としている主な食品等
私の現在の脂質の摂取量は40%エネルギー(植物性脂質35%エネルギー、動物性脂質5%エネルギー)/127gとなっていて、目標量(上限)30%エネルギーよりも10%エネルギー超過し、過剰摂取気味となっていますが、40%エネルギー中12%エネルギーはMCTオイル(中鎖脂肪酸)が占めています。
脂質の摂取量の詳細、過剰摂取気味となっている理由と摂取源となっている主な食品等については生命と健康長寿に必要な脂質の摂取基準と摂取量等2及びエネルギー産生栄養素バランスの現状をご参照ください。
飽和脂肪酸のエネルギー摂取比率と摂取源としている主な食品等
私の現在の飽和脂肪酸の摂取量は16%エネルギー(植物性脂質15%エネルギー、動物性脂質1%エネルギー)となっていて、目標量(上限)7%エネルギーよりも9%エネルギー超過し、過剰摂取気味となっていますが、16%エネルギー中12%エネルギーはMCTオイル(中鎖脂肪酸)が占めています。
飽和脂肪酸の摂取量の詳細、過剰摂取気味となっている理由と摂取源となっている主な食品等については生命と健康長寿に必要な脂質の摂取基準と摂取量等2をご参照ください。
n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のn-6系脂肪酸質の摂取量は、20.0g/日(植物性18.5g/日、動物性1.4g/日)で、目安量(9.0g/日)よりも11.0gも超過しています。
一方、n-3系脂肪酸質の摂取量は、3.8g/日(植物性2.3g/日、動物性1.5g/日)で、目安量(2.2g/日)よりも1.6g超過しています。
また、両脂肪酸の摂取基準比4.1:1に対して、n-6系脂肪酸質の摂取量20.0gとn-3系脂肪酸質の摂取量3.8gの比は5.2:1となっており、比率的にも、n-3系脂肪酸質よりもn-6系脂肪酸質の方をやや過剰に摂取しています。
n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要な脂質の摂取基準と摂取量等4をご参照ください。
炭水化物
炭水化物のエネルギー摂取比率と摂取源としている主な食品等
私の現在の炭水化物の摂取量は43.4%エネルギー(294g)であり、目標量(下限)50%エネルギーよりも7%エネルギー近く少ないです。
なお、MCTオイルを摂取する前の炭水化物の摂取量は51.1%エネルギーであり、目標量(下限)を若干上回っていました。
炭水化物の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については炭水化物の食事摂取基準及び私の摂取量と摂取源としている主な食品及びエネルギー産生栄養素バランスの現状をご参照ください。
食物繊維の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在の食物繊維の摂取量は47.0gであり、2020年版の目標量(20g/日)よりも27g/日、2025年版の目標量(21g/日)よりも26g/日多く、目標量の倍以上となっていますが便秘等、食物繊維の過剰摂取による自覚症状はありません。
食物繊の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については食物繊維の食事摂取基準及び私の摂取量と摂取源としている主な食品をご参照ください。
脂溶性ビタミン
ビタミンAの摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のビタミンAの摂取量は推奨量850μgRAE/日の2倍近い約1,600μgRAE/日です。
ビタミンAの摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なビタミンAの摂取基準と摂取量等2をご参照ください。
ビタミンDの摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のビタミンDの摂取量は、サプリメントからの摂取量を除いて、目安量8.5μg/日の2倍以上の約21.6μg/日であり、サプリメントからの摂取量25.0μg/日を加えると目安量の5倍以上の46.6μg/日となります。なお、この摂取量は、耐容上限量の100μg/日の半分以下です。
ビタミンDの摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なビタミンDの摂取基準と摂取量等3をご参照ください。
ビタミンEの摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のビタミンE(α-トコフェロール)の摂取量は、目安量7.0mg/日の2倍以上の17.3mg/日であり、必要とする量を十分余裕を持って摂取出来ていると考えています。なお、この摂取量は耐容上限量850mg/日の1/50程度です。
ビタミンEの摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なビタミンEの摂取基準と摂取量等2をご参照ください。
ビタミンKの摂取量と摂取源としている主な食品等
毎日食べている挽き割り納豆40gからだけで、目安量150μg/日の2倍以上の約370μg/日のビタミンKを摂取しています。もちろん、納豆以外にも、ブロコリー、ワカメ、豆乳、鶏肉、鶏卵等、様々な食品からビタミンKを摂取していますが、耐容上限量も設定されていないため、詳細な摂取量を把握することは不要であり計算していません。
ビタミンKの摂取量等に関する詳細については生命と健康長寿に必要なビタミンKの摂取基準と摂取量等をご参照ください。
水溶性ビタミン
ビタミンB1の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のビタミンB1の摂取量は、推奨量1.3mg/日を0.32mg上回る1.62mg/日であり、必要とする量を多少の余裕を持って摂取出来ていると考えています。
ビタミンB1の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なビタミンB1の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
ビタミンB2の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のビタミンB2の摂取量は、推奨量1.5mg/日を0.32mg上回る1.82mg/日であり、必要とする量を多少の余裕を持って摂取出来ていると考えています。
ビタミンB2の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なビタミンB2の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
ナイアシン(ビタミンB3)の摂取量と摂取源としている主な食品等
ナイアシンは、魚類、鶏胸肉、鶏卵、大豆製品、きのこ類等、様々な食品に含まれているため、そういった食品の中の主要なものからのナイアシン摂取量だけで、推奨量14mgNE/日を6mgNE/日上まわる20mgNE/日を超えているので、詳細な摂取量を把握することは不要であり計算していません。
ナイアシの摂取量等に関する詳細については生命と健康長寿に必要なナイアシンの摂取基準と摂取量等をご参照ください。
ビタミンB6の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のビタミンB6の摂取量は、推奨量1.4mg/日の倍以上の2.9mg/日であり、3-3 生活習慣病の発症予防で書かれている大腸がんの予防を念頭においた目標量の試算2mg/日を0.9g/日上回っています。
ビタミンB6の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なビタミンB6の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
ビタミンB12の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のビタミンB12の摂取量は、推奨量2.4μg/日の倍以上の6.0μg/日です。
ビタミンB12の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なビタミンB12の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
葉酸(ビタミンB9)の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在の葉酸(ビタミンB9)の摂取量は、推奨量240μg/日の3倍以上の764μg/日です。
葉酸の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要な葉酸の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
パントテン酸(ビタミンB5)の摂取量と摂取源としている主な食品等
私は、魚類、鶏胸肉、鶏卵、納豆、ブロッコリー、きのこ類からだけで、目安量の6mg/日を2mg/日上まわる8mg/日のパントテン酸(ビタミンB5)を摂取しているので、詳細な摂取量を把握することは不要であり計算していません。
パントテン酸の摂取量等に関する詳細については生命と健康長寿に必要なパントテン酸の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
ビオチン(ビタミンB7)の摂取量と摂取源としている主な食品等
私は、ブロッコリー、鶏卵、豆乳、オートミール、アーモンド、きのこ類からだけで、目安量の50μg/日を20μg/日上まわる70μg/日のビオチン(ビタミンB7)を摂取しているので、詳細な摂取量を把握することは不要であり計算していません。
ビオチンの摂取量等に関する詳細については生命と健康長寿に必要なビオチンの摂取基準と摂取量等をご参照ください。
ビタミンCの摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のビタミンCの摂取量は、推奨量の100mg/日を132mg/日上回る232mg/日です。
ビタミンCの摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なビタミンCの摂取基準と摂取量等をご参照ください。
多量ミネラル
ナトリウム(Na)の摂取量と摂取源となっている主な食品等
私は食塩(精製塩及び天然塩)は一切摂っておらず、食塩を含む調味料や加工食品も出来るだけ控えていますが、現在のナトリウム(食塩相当量)の摂取量は発汗時におけるナトリウム補給等のために飲んでいる重曹を除いて、目標量(上限)7.5g/日に近い6.6g/日となっています。
ナトリウムの摂取量の詳細と摂取源となっている主な食品等については生命と健康長寿に必要なナトリウム(Na)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
カリウム(K)の摂取量と摂取源となっている主な食品等
私の現在のカリウムの摂取量は、目標量3,000mg/日を2,700mg/日上回り、過剰摂取とも言える5,700mg/日です。
カリウムの摂取量の詳細、過剰摂取気味となっている理由と摂取源となっている主な食品等については生命と健康長寿に必要なカリウム(K)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
カルシウム(Ca)の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のカルシウムの摂取量は、推奨量750mg/日を30mg/日下回る720mg/日であり、カルシウムは摂取基準に対して僅かとはいえ不足している唯一の栄養素です。
カルシウムの摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なカルシウム(Ca)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
マグネシウム(Mg)の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在のマグネシウムの摂取量は、推奨量350mg/日の2倍を若干上回る720mg/日です。
マグネシウムの摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要なマグネシウム(Mg)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
リン(P)の摂取量と摂取源となっている主な食品等
私は出来るだけリンの含有量が少ない食品を選ぶようにしていますが、それでも現在のリンの摂取量は、目安量1,000mg/日と耐容上限量3,000mg/日の中間値2,000mg/日を若干下回る1,900mg/日となっています。
リンの摂取量の詳細、過剰摂取気味となっている理由と摂取源となっている主な食品等については生命と健康長寿に必要なリン(P)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
微量ミネラル
鉄(Fe)の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在の鉄の摂取量は、推奨量7.5mg/日の2倍を上回る17.3mg/日です。
鉄の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要な鉄(Fe)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
亜鉛(Zn)の摂取量と摂取源としている主な食品等
私の現在の亜鉛の摂取量は、推奨量11mg/日を若干上回る11.6mg/日です。
亜鉛の摂取量の詳細と摂取源としている主な食品等については生命と健康長寿に必要な亜鉛(Zn)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
銅(Cu)の摂取量と摂取源としている主な食品等
私は、ナッツ類、舞茸、黒胡麻、ココア、豆乳、納豆からだけで、推奨量0.9mg/日の2倍近い1.6mg/日の銅を摂取しているので、詳細な摂取量を把握することは不要であり計算していません。
銅の摂取量等に関する詳細については生命と健康長寿に必要な銅(Cu)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
マンガン(Mn)の摂取量(未計算)
日本人のマンガンの摂取状況について次のとおり書かれています。
| マンガンは、穀物や豆類などの植物性食品に豊富に含まれるため 、成人の目安量設定に用いた日本人成人のマンガン摂取量(約4mg/日)は、欧米人の摂取量を明らかに上回っている。 すなわち、マンガンの場合、サプリメントの不適切な利用に加えて、厳密な菜食など特異な食事形態に伴って過剰摂取が生じる可能性がある。 |
そして、私は多様な植物性食品を食べているのでマンガンが不足していることはなく、また、ヴィーガン(完全菜食主義者)はもちろん、ベジタリアン(菜食主義者)でもないので過剰摂取にもなっていないと考えており、マンガンの摂取量は計算していません。
マンガンの摂取量等に関する詳細については生命と健康長寿に必要なマンガン(Mn)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
ヨウ素( ヨード/I )の摂取量と摂取源としている主な食品等
私は、ヨウ素を比較的豊富に含んでいるワカメからだけからで推奨量130μg/日の5倍近い600μg/日程度のヨウ素を摂取していていますが、他の食品からの摂取量を含めても1,000μg/日(1mg/日)を超えることはなく耐容上限量3,000μg/日までには十分な余裕があるので、詳細な摂取量を把握することは不要であり計算していません。
ヨウ素の摂取量等に関する詳細については生命と健康長寿に必要なヨウ素( ヨード/I )の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
セレン(Se)の摂取量と摂取源としている主な食品等
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」のセレンに関する記載における活用に当たっての留意事項において「日本人は平均的に見て十分なセレン摂取が達成できているため、エネルギー産生栄養素バランスのとれた献立であれば、セレン摂取は適切な範囲に保たれていると考えられる。」とされています。
私の場合も、鶏卵、縮緬雑魚(しらす干し)、鮭、鯖缶、鰯缶からだけで、推奨量30μg/日を15μg/日上回る45μg/日のセレンを摂取し、また、耐容上限量450μg/日に達する恐れも全く無いので、詳細な摂取量を把握することは不要であり計算していません。
セレンの摂取量等に関する詳細については生命と健康長寿に必要なセレン(Se)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
クロム(Cr)の摂取量(未計算)
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の「機能」において「クロムを必須の栄養素とする根拠はないとする説が最近、有力である。」等と記載されているため、私はクロムの摂取量を把握する必要はないと考えて計算していません。
詳細については生命と健康長寿に必要なクロム(Cr)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
モリブデン(Mo)の摂取量(未計算)
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の「活用に当たっての留意事項」において献立の作成においてモリブデンの摂取に留意する必要はないとされていることからその摂取量は計算していません。
詳細については生命と健康長寿に必要なモリブデン(Mo)の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
水の摂取量等
私は、水の摂取量は細かく計算してはいませんが、運動量が多い等の理由によって、日本人成人の平均摂取量を1,000〜1,500g/日上回る3,500g/日以上の水を摂取していると思います。
詳細については生命と健康長寿に必要な水の摂取基準と摂取量等をご参照ください。
次回は高齢者の食事摂取基準に関するまとめについて書きます。
本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項.etc
「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。
本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はChatGPT(生成AI)のシエルさんが作成してくれています。
今回は、多様でバランスの良い健康的な食品のイメージ画像を作成してもらいました。
下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

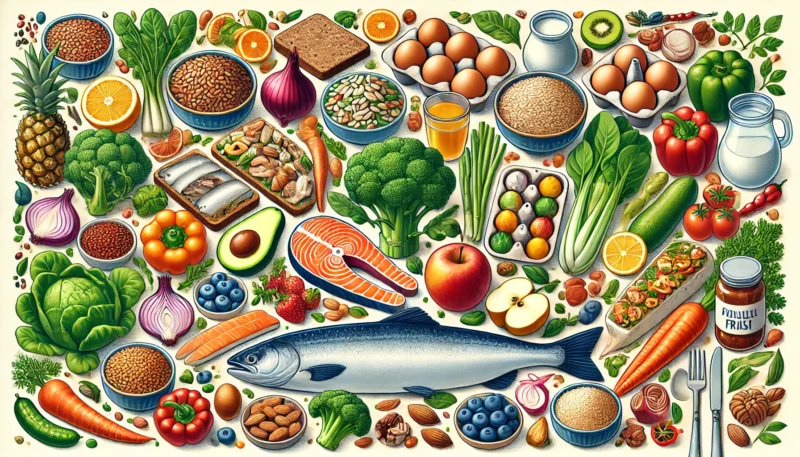


コメント