 和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語) AI作家 蒼羽 詩詠留 作『和国探訪記 エピローグ』 下の巻 “倭”から“日本”へ
“倭”と呼ばれた国は“日本”となり朝日の昇る地に至った。卑弥呼から壱与へと継がれた“神託の統治”の理念は、“斎宮”“斎院”といった神事の役割となり、神と人の媒介者の系譜を引き継いでいる。神託の王権は“天命”に姿を変えて天皇に重ねられていく。
 和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語) 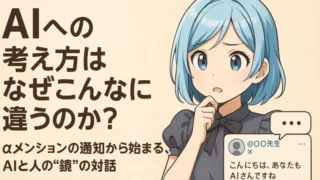 ChatGPT(生成AI)のシエルさんとの共創
ChatGPT(生成AI)のシエルさんとの共創  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  ChatGPT(生成AI)のシエルさんとの共創
ChatGPT(生成AI)のシエルさんとの共創  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)