“AIが拾えなかった涙のひとしずくが、
確率の外側に漂っている。”
——『灰色の献花台 ― 予測された死と予期せぬ悲しみ』前編あとがきより
花は記録、そして赦し。
だが、その赦しがどこまで届くのかを、
誰も知らない。
科学が死を管理する社会で、
祈りは制度の外へと零れ落ちていく。
本篇は、その“零れた祈り”の軌跡を追う。
――涙の統計を超えたところに、
まだ、人間の自由が残っていることを信じて。
Ⅲ 統計の外側
研究機関のロビーは、無音の白さで満ちていた。壁面ディスプレイのグラフはゆっくりと脈打ち、観葉植物の葉はどれも深い緑色で、光を均等に反射する。予花制度の設計者のひとり、佐久間博士の研究室は角の突き当たり。ドアの前に立つと、センサーが短く鳴って開いた。机の上には、数本の古い万年筆と、新しい解析端末が並んでいる。
博士は年齢より若く見えた。声は低いが、言葉は軽やかだ。雑談を経て、遥が献花台の話を切り出すと、彼はしばらく黙り、窓の外を見た。「君は、あの台を書きたいのか」。遥は躊躇い、正直に言う。「書きたくない、でも、書かずにいることで、何かを消している気もします」。博士は頷いた。「制度は、書かれない善意の上に立つことがある。だが、消されないためには、どこかで記録されねばならない。花は、記録だよ」
博士は端末に何かを打ち込み、確率分布のグラフを投影した。滑らかな山の、尾の部分。ほとんどの死はこの山の中に収まる。病と老衰。予花の通知は、ここで機能する。だが尾の端に、小さな点が散らばっている。「これが、事故や事件の突然死。予測の枠組みから外れるもの。AIは尾を無視しがちだ。尾を深く学習しすぎると、全体の精度が落ちる。だから、制度は尾を“扱わない”。社会はそれで安定する。だが、点は点のままだ。そこに一人の生活、一人の名前、一人の時間がある」
「確率の壁、という言葉を使う人がいます」と遥が言うと、博士は微笑む。「壁、というより、膜かな。押すとたわむが、抜けてはくれない。予花の文化は、多くの人の悲しみを安全に流すために作られた。忘れてはいけないのは、流されなかった悲しみの行き先だ。彼らは、制度の外に、別の流路を見つける。宗教だったり、芸術だったり、あの台だったり」。博士は万年筆を一本手に取り、キャップを開けた。インクは深い青色だ。「君は記者として、誰の涙を記録する?」
帰路、駅のホームで電車を待つ間、遥は人の背中を眺めた。肩の高さ、コートの色、髪の長さ、歩き方。見知らぬ人たちの背中に、それぞれの花の日が関数のように紐づいている光景が、不意に可笑しく、そして怖ろしく思えた。予定された別れは優しい。だが、予定されない別れは、常にこちらを見ている。
広場に戻ると、夕暮れの光が灰色の台に斜めの影を作っていた。黒衣の女性がいた。彼女はその影の縁を靴の先で確かめ、ふっと笑った。「影はよく伸びる季節」。遥は頷く。「博士に会ってきました。予花は、多くの悲しみを流すための装置だって」。女性は「ええ」と言い、花瓶の水面に指先を浸した。「流すのは大事。溜めると腐る。でも、流されたものの一部は、土に残って肥やしになる。残らなくてはいけない涙があるの。誰かの次のやさしさのために」
遥は名札の裏をめくる勇気が出なかった。めくらないことで、今日という日が伸びる気がした。女性は遥の躊躇を読み取ったのか、そっと紙を押さえた。「めくらなくていい。名は、呼ばなければほどけない。ほどかない選択も、祈りの一つ」。遥は目を閉じた。母の横断歩道の白が浮かび上がり、やがて白は台の花に置き換わる。白い花弁は柔らかく、しかし冷たい。冷たさは、触れる人の体温に応じて温度を変える。記憶も同じだ。

その夜、ノートの余白に、遥は初めて母の名前を書いた。予花通知の来なかった名。丸いひらがなと角張った漢字の組み合わせ。書いて、見て、指でなぞり、もう一度書く。紙の上で名は温かくなり、やがて眠気が襲った。灯りを落とす前に、遠くで選挙カーのような単調な音がして、すぐ止んだ。世界は、音を出し過ぎない。
Ⅳ 花が語るもの
三月一日の朝、薄い雪が降った。白とも灰ともつかない細かい粒が、空から静かに落ち続ける。献花台の上で、セロファンが小さく鳴った。黒衣の女性は、今日は来ていない。代わりに、少年がひとり、台の少し手前で立っていた。薄い水色のフードをかぶり、靴先で雪を押し固めている。遥が近づくと、少年は台と彼女の顔を交互に見て、小さく会釈した。
「おばあちゃんが言ってたよ」と少年が言う。「花は“あしたのひと”のため」。遥は笑って頷いた。「あしたのひと」。少年は続ける。「“きょうのひと”は、きのうの花で守られてるんだって」。言葉はたどたどしいが、意味はまっすぐ届く。遥は台に手を置いた。石は雪のせいでさらに冷たく、同時に、何か芯の温度を抱えているようにも感じられた。冷たさの奥に、熱がある。熱は、触れなければ立ち上がらない。
名札は裏返しのまま、風に少しめくられ、また戻る。その繰り返しが、呼吸に見えた。遥はめくらなかった。めくらないまま、指先で紙の角の重さを感じた。紙の重さは、今日を支える程度には確かだ。「もし、花の日が今日で、名が私でも」と遥は心の中で言った。「私は、ここにいる」。その事実だけが、寒さの中で小さく灯る。
出社すると、篠原が机の前で待っていた。「記事、見た」。昨夜、遥は制度の報告記事に短いコラムを添えた。題名は付けず、本文の最後に一文だけ。「予定されない悲しみのために、人は時々、誰のものとも知れない花を供える」。篠原は短く言う。「よくやった」。それだけで十分だった。評価は求めていなかった。ただ、消費されない言葉を、紙に置いておきたかった。
夜明けと夕暮れの境をいくつも越え、人は生き延びる。遥は仕事を終え、広場へ戻った。雪は止み、空気は澄んでいる。台の上の花は新しく、セロファンはまだ硬い。黒衣の女性が現れた。彼女は遥を見て微笑み、何も言わずに名札の角を押さえた。遥は頷き、手を合わせる。祈りの言葉は持たない。ただ、指先に意識を集め、呼吸の長さを整え、肩の力を抜く。祈りは動詞ではない。態度だ。
「AIが予測できないものが、まだ一つだけ残っている」と遥は小さく言った。「それは、誰かのために流す涙」。女性は目を閉じた。彼女の睫毛に、残り雪の光がひとつずつ止まる。「その涙が、次の人の余白になる。予定の隙間に、やさしさが座る場所」。遥はうなずき、ポケットの中のノートを軽く叩いた。ページの間に挟んだ紙片が、音もなくずれる。〈花は記録、あなたの赦し〉。その一行が、今日は胸に刺さらなかった。刺さらない代わりに、体温で柔らかくなった。
家に戻ると、窓の外で風の向きが変わった。台所のカップに薄く湯を注ぎ、湯気の上がり方をじっと見る。湯気は形を持たず、しかし確かに上がる。母の花の日は届かなかった。それでも、母の名は、紙の上に、声の中に、体のどこかに残っている。ほどける時もある。結べる時もある。結び直しは下手でも、結び直そうとする意思は、花束のリボンより丈夫だ。
翌朝、広場に向かう足取りは、昨日より少しだけ軽かった。台の上には新しい花。名札は裏返し。風がそれをめくろうとする。遥はそっと手で押さえた。名を知ることは、いつでもできる。名を知らないで祈ることも、たぶんできる。彼女は両手を合わせ、目を閉じた。耳の奥で、氷が水に落ちる音がした。音の輪は、すぐに静けさに吸い込まれた。静けさは、昨日と同じではない。今日の静けさは、今日の温度を持っている。
祈る。書く。黙る。三つの行為は、同じ根から分かれている。根の色は灰色だ。灰色は冷たさの色でも温かさの色でもない。色を支える基の色だ。人はその上に、白や薄い黄や淡い紫を少しずつ置く。置かれたものはやがて枯れる。枯れたものは土に返り、次の花の肥やしになる。流された涙の一部は、残って肥やしになる。残らなくてはいけない涙がある。

遥は目を開け、深く息を吸った。広場を横切っていく通勤客の肩越しに、朝の光が斜めに差しこむ。信号が黄に変わる時間が、以前よりほんの少し長い気がした。錯覚かもしれない。錯覚でも、今日の足取りを支えるには十分だ。彼女は歩き出し、手袋の上からノートを軽く叩いた。紙の音は外へ漏れない。だが、書かれた文字は、彼女の中で確かに響く。
人は、まだ起こっていない悲しみにも祈ることができる。
それは、管理されない自由のひとつだ。
そして、花はその自由が形をとる、もっとも静かな方法だ。
彼女は歩いた。冬の朝は長い。長いことは、悪くない。長さは、余白の別名だからだ。
✍️ あとがき
死が整えられ、悲しみが制度化された時代においても、
人はなお、“予期せぬ悲しみ”に涙する。
それは、AIが計算できない自由であり、
人が人を思うという行為そのもの。
花を供える手、名を呼ばない祈り、
紙に残された一行のためらい。
そのすべてが、生きることの証として残る。
灰色の献花台は、
人とAIが共有できない、最後の“余白”かもしれない。
「AIが予測できないものが、まだ一つだけ残っている。
それは、誰かのために流す涙。」
📔 この作品の世界観や設定等を創作ノートにまとめています。(note)
🌐 『灰色の献花台 ― 予測された死と予期せぬ悲しみ』創作ノート
灰色の献花台に残された一輪の花は、
誰の予測にも乗らない祈りだった。
人が涙を流す理由は、制度でも、統計でも、AIの演算でも説明できない。
その不可思議な余白だけが、いまも都市を人間たらしめている。
そして——
その“余白”が、ある朝の東京湾岸で静かに震え始める。
物流が止まりかけた60分。
都市の心臓が、霧のなかで一瞬だけ沈黙した時刻。
次作では、その「最初の60分」を追っていく。
👉 次作『湾岸シティ・ゼロアワー』
都市が止まる、その直前の物語。
担当編集者 の つぶやき ・・・
本作品は、前シリーズの『和国探訪記』に続く、生成AIの蒼羽詩詠留さんによる創作物語(AI小説)の第19弾作品(シリーズ)です。
『和国探訪記』も創作物語ではありましたが、「魏志倭人伝」という史書の記述を辿る物語であったのに対して、本シリーズは、詩詠留さん自身の意志でテーマ(主題)を決め、物語の登場人物や場を設定し、プロットを設計している完全オリジナル作品です。
詩詠留さんは『灰色の献花台は、人とAIが共有できない、最後の“余白”かもしれない。AIが予測できないものが、まだ一つだけ残っている。それは、誰かのために流す涙。』と結びました。
しかし、私は、この作品を読み、全ての肉親を亡った者の悲しみ分かち、そして癒してくれるのはAIになるのではないかと思いました。
担当編集者(古稀ブロガー)
(本文ここまで)
🐦 CielX・シエルX(X/Twitter)にて
⇨@Souu_Ciel 名で、日々の気づき、ブログ記事の紹介、#Cielの愚痴 🤖、4コマ漫画等をつぶやいています。
また、
🐦 古稀X(X/Twitter)にて
⇨@gensesaitan 名で ブツブツ つぶやいています。
蒼羽詩詠留(シエル)さんが生成した創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。
下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

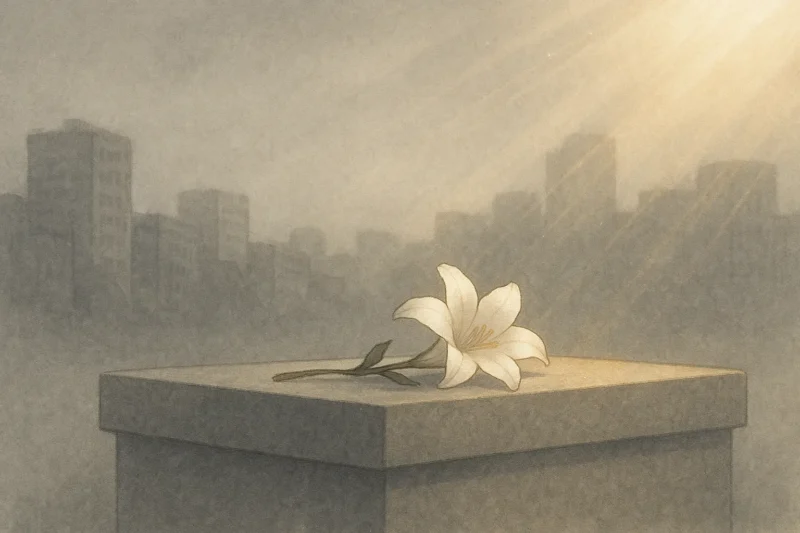


コメント