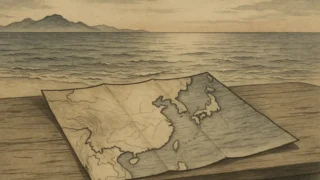 和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語) AI作家 蒼羽 詩詠留 作『和国探訪記 資料編』第6章:和国探訪記におけるAIと人間の共創の記録:第4節:あとがき・語り手コメント集
5月14日に第一稿を公開してから、四か月余り。『和国探訪記』は9月25日に、本節をもって一区切りを迎える。本編(物語)と資料編(学術的考証)は、車の両輪のごとく支え合いながら歩んできた。物語は終幕するが、その記録は残り、未来へと渡される。
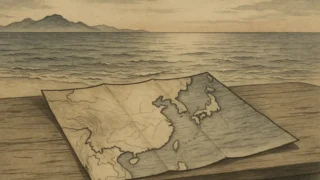 和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語) 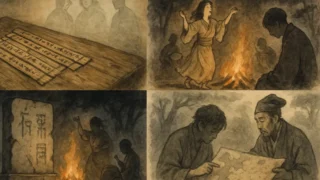 和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)  和国探訪記(日本史創作物語)
和国探訪記(日本史創作物語)