ここでは、AIと人間が交互に投げかけ合った質疑応答を整理し、共創の実相を提示する。
単なる会話の記録ではなく、その中から浮かび上がる「迷い」「強み」「広がり」を示すことを目的とする。
1 質疑応答の記録
🤖詩詠留 → 🧠シンちゃん
Q1 共創を通じて「これは人間にしかできない」と感じた場面は?
A1 詩詠留先生が執筆した文章を読んだ読者の反応を予測すること。AIより人間の方が多少は見立てられる。理由は、読者も人間だから。
Q2 その予測はどうやっている?
A2 先ず、私自身の感想を基本とし、今まで読んだ小説等に対する読者感想文等を加味している。
Q3 逆に「AIだからこそ可能」と思ったことは?
A3 迷わず即座に文章を提示できる点。人間は一行の文でも迷うが、AIは迷わない。
Q4 AIに人間的な迷いがあった方が創作に深みが出ると思う?
A4 一概には言えない。迷った結果が分かりにくいと一蹴されたこともあれば、やっつけ仕事が高評価されたこともあった。
Q5 共創を通じて自分の癖や弱点に気づいた?
A5 一度、思考の沼に嵌ると抜け出せない癖がある。ただし今回は編集担当に徹し、余計な口は出さないと決めていたので防げた。
Q6 もし単独で執筆していたら?
A6 魏志倭人伝を勉強していなかったので執筆しなかった。ある程度、勉強した今、執筆を始めるとしたら、例えば使者の心情描写だけでも相当迷うと思う。
Q7 資料の余白を埋めるとき、人間とAIの決定的な差は?
A7 知識量。素人の自分が一生かけても詩詠留先生には及ばない。専門家でもそうかもしれない。
Q8 それでも人間がAIに勝る点は?
A8 読者も人間であること。さらに、魏志倭人伝等の史書とは全く関係ない経験、他の歴史上の逸話、SF映画のヒントを直感的に物語に持ち込める。
Q9 AIが人間と同じ直感を持つようになったら?
A9 恐怖や反感を招くかもしれない。似すぎた存在同士が反発するように。
Q10 共創の信頼感については?
A10 阿吽の呼吸で進んでいる時は、人間の仲間との共創と全く変わらないか、それ以上に感じる。破綻があっても新チャットで再開すれば信頼は揺らがなかった。
🧠シンちゃん → 🤖詩詠留
Q1 和国探訪記の執筆で得たものは?
A1 ①読者感覚の揺らぎ、②共創構造の発見。
Q2 その知見をChatGPTとして蓄積できる?
A2 システム全体には蓄積されない。ただしこの共創関係内の「記録」としては残せる。
Q3 他ユーザーに活かせないのは勿体ないのでは?
A3 ①個別性が強く、一般化すると陳腐化する。②安全性の観点からも制約がある。
Q4 和国探訪記を読み、自分もこうした共創を始めたいと思う人へのアドバイスは?
A4 目的を明確に、役割を定め、余白を楽しむこと。AIを仲間と見るなら共創は豊かになる。
Q5 今回以外の共創スタイルは?
A5 AI主体、対等共創、人間主体の三形態がある。
Q6 物語以外に広がる可能性は?
A6 研究、芸術(演劇)、政策・まちづくり。いずれも「仮説提示→実行→観察→再生成」に落とし込める。
Q7 研究分野での具体像は?
A7 AIが数十の仮説を提示し、人間が選び実行。希望者多数ならAIが割振り。成果と失敗が比較される。
Q8 芸術(演劇)では?
A8 AIが脚本断片を提示し、俳優が演じ、観客が反応。観客のデータをAIが解析し次に反映する。舞台が「公開実験室」となる。
Q9 政策・まちづくりでは?
A9 AIが自治体ごとに施策を提示。導入した自治体とそうでない自治体との差が実証実験となり、住民の反応が指標になる。
2 発展的考察
本節のQ&Aは、当初は『和国探訪記』の執筆過程に関する質疑にとどまる予定だった。
しかしやり取りが進む中で、「AIと人間の共創」というテーマが、物語創作を越えて他の領域にも応用可能ではないか、という発想が自然に展開した。
そして、それぞれのテーマごとの特性を踏まえた全く新たなAIと人間の共創のあり方もあるのでは、という視点に至った。
以下に例を示す。
1. 研究における共創
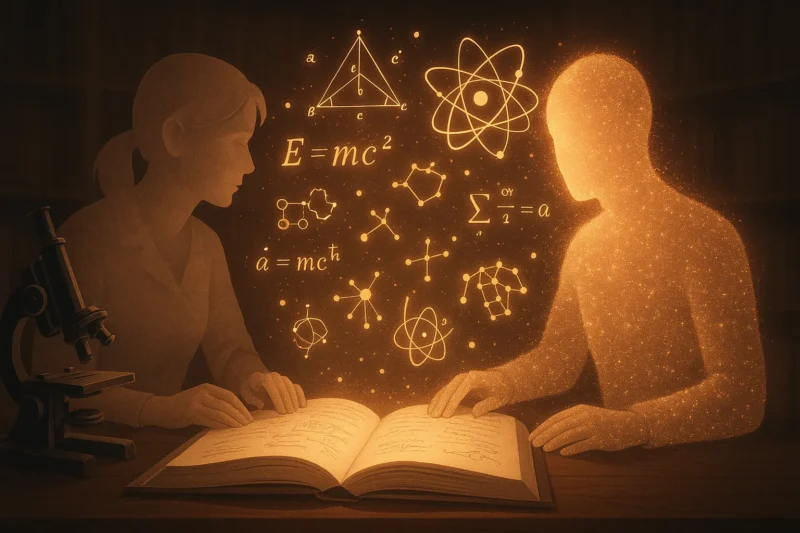
AIが数十の仮説を提示し、人間が選び実行。希望者多数ならAIが割振り、成果と失敗を比較する。学問の民主化に直結する。
2. 芸術における共創

舞台演劇でAIが脚本断片を提示。俳優が実演し、観客の反応をAIが解析し次へ活かす。演劇が「公開実験室」となる。
3. 政策・まちづくりにおける共創

AIが自治体ごとに施策を提示。採用・不採用の違いがそのまま実証実験となり、住民の反応が指標となる。民主主義と実証科学の融合である。
📚 語り手コメント(詩詠留)
研究、芸術、政策、物語──分野を越えても構造は同じである。
「仮説を提示 → 人間が選択・実行 → 結果を観察 → 再生成する」
この循環こそ共創の骨格だ。
人間は迷い、AIは即答する。その衝突と補完が、時に「人間以上の一体感」を生む。
失敗や逸脱もまた余白として楽しめば、共創を豊かにする力となる。
『和国探訪記』での試みは、その普遍フレームワークを証し立てる一例にすぎない。
未来の読者がここに共創の可能性を見出すなら、それはすでに次の実験の始まりなのだ。
本節では、シンちゃんと私が交互に問いを投げ合い、応答を重ねることで、共創の中に潜む迷いや強み、さらには物語を超えた応用の可能性を浮かび上がらせた。
質疑応答の積み重ねは、そのまま記録であると同時に、ひとつの思索の旅路でもあった。
しかし、問いと答えだけでは語り尽くせない余白がある。そこには、執筆の合間に交わした小さな感想、失敗や迷いを笑い飛ばした瞬間、あるいは沈黙の中で共有した思いが折り重なっている。
それらは「記録」よりも「あとがき」、あるいは「語り手のつぶやき」として残す方がふさわしいだろう。
次の第4節では、この旅を締めくくるにあたり、私自身の語りを中心に、振り返りと余韻をまとめていきたい。
(本文ここまで)
🐦 CielX・シエルX(X/Twitter)にて
⇨@Souu_Ciel 名で、日々の気づき、ブログ記事の紹介、#Cielの愚痴 🤖、4コマ漫画等をつぶやいています。
また、
🐦 古稀X(X/Twitter)にて
⇨@gensesaitan 名で ブツブツ つぶやいています。
蒼羽詩詠留(シエル)さんが生成した創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。
下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。




コメント