 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等 二度目の人生における健康的な食生活 77~生命と健康長寿に必要なカルシウム(Ca)の摂取基準と摂取量等
カルシウムの過剰摂取により高カルシウム血症、高カルシウム尿症、軟組織の石灰化、泌尿器系結石、前立腺がん、鉄や亜鉛の吸収障害、便秘などが生じる可能性。カルシウムの摂取と高血圧や肥満など生活習慣病とは負の関連。ビタミンDはカルシウム吸収を促進
 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等 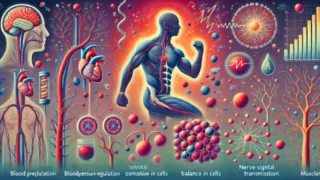 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等  生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等 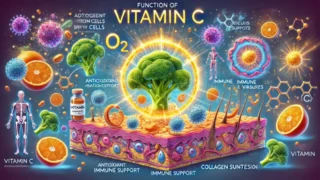 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等 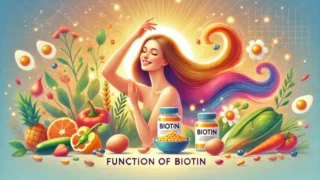 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等 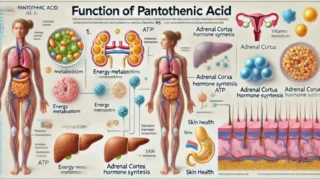 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等 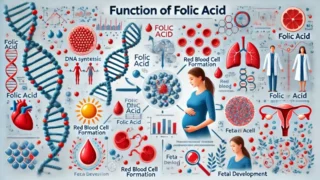 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等 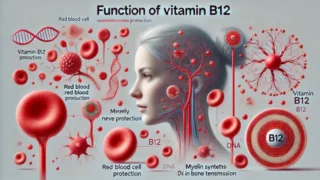 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等 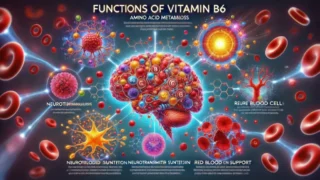 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等 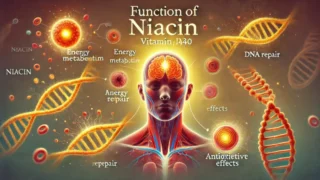 生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等
生命と健康長寿に必要な栄養素の摂取基準と摂取量等